
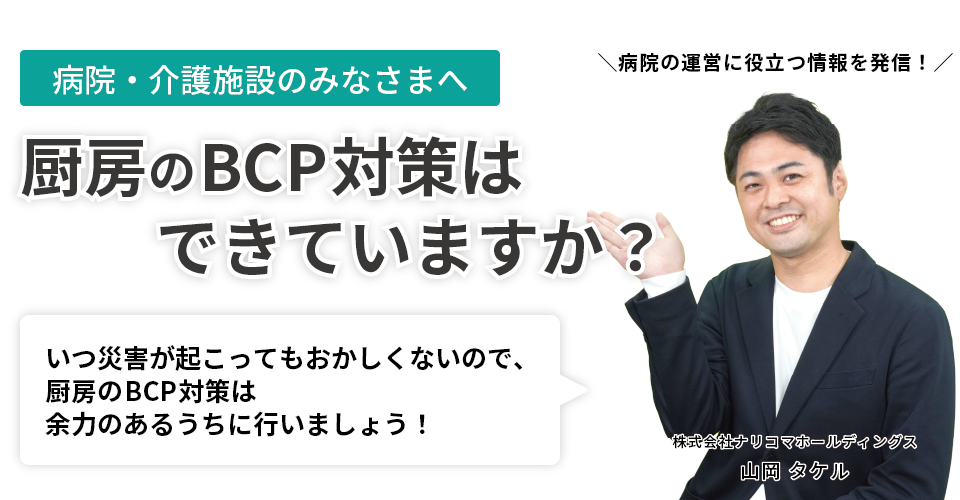

日本では災害が多く、毎年のように地震、台風、豪雪などの大規模な自然災害が起こっています。
特に、「南海トラフ地震」は今後30年以内に70〜80%の確率で発生すると予測されており、まさに自然災害がいつ起こってもおかしくない状況です。
自然災害に遭うと、ライフラインの分断が起こることもあり、食事の確保が困難になったり避難所生活になることもあります。
病院や介護施設では、患者さま・利用者さま・職員さまの生活を守り、安定したサービスを提供するため、平常時からの対策は必須ですよね。
そのような背景から、2017年に災害拠点病院の事業継続計画(以下、BCP)が義務化されました。
さらに、2024年3月までには全介護事業者へのBCP策定が義務化されます。
また、災害拠点病院以外でも、患者さまのことを考えてBCP策定を進められている病院さまは多くいらっしゃいます。
煩雑なBCP書類作成も、ポイントをつかめばスムーズに進めることができます。
もし、策定にお困りなら動画にて解説していますのでご覧ください。
厨房のBCP対策といえば、主に非常食のことを考える方は多いはず。
しかし実際には、非常食以外にも必要な対策があります。

大地震や自然災害時には電気・ガス・水道が使えなくなる可能性があります。
電気・ガス・水道が使えない場合、通常通りの調理ができないため対策が必要です。
非常食の用意はもちろんのこと、厨房業務における周辺のことも考えておいたほうがよいでしょう。
また、食事の加熱にはガスが必要なため、LPガスやカセットコンロなどを用意しておくなどの対策が取れます。
生活に欠かせない水は、飲み水だけではなく生活用水の確保のため給水所の場所を把握することも考えなければいけません。
このように、自然災害時でも食事提供に支障がないように準備していきましょう。

自然災害時には安否確認や、その後の勤務体制を考えるうえでの連絡や指示出しが欠かせません。
企業には、労働契約法第5条の「労働者の安全への配慮」に記されている通り、安全配慮義務があります。安否確認自体に義務はありませんが、職員の安全を守るために取り組むべきことと言えます。
また、被災してしまうと、地割れや土砂災害などで通行止めになるなど、職員が通常通り出勤できなくなる可能性があります。勤務体制を考えるうえでも、連絡・指示の手段は考えておく必要があります。
例えば、緊急連絡網を作る、安否確認システムを導入する、指示者が出勤できなかった場合の代理を立てておくなどの対策を取りましょう。

特に厨房は管理栄養士・栄養士・調理師など専門的な職種の方が多く働いています。
そのため、自然災害時に特定の資格を持った職員が出勤できなくなる可能性があります。
いざ食事を提供するとなった場合、提供方法がわからないなどの事態にも陥りかねません。
専門職が不在でも食事が提供できる仕組みを取り入れることで、自然災害時にも食事を提供できる体制が作れます。
誰にでも提供できる仕組みを作るためには、調理済み食品の活用で実現が可能です。
このように、平常時から属人化をせず安定した食事提供ができる仕組みを作ることが、自然災害時にも動けるBCP計画へとつながります。