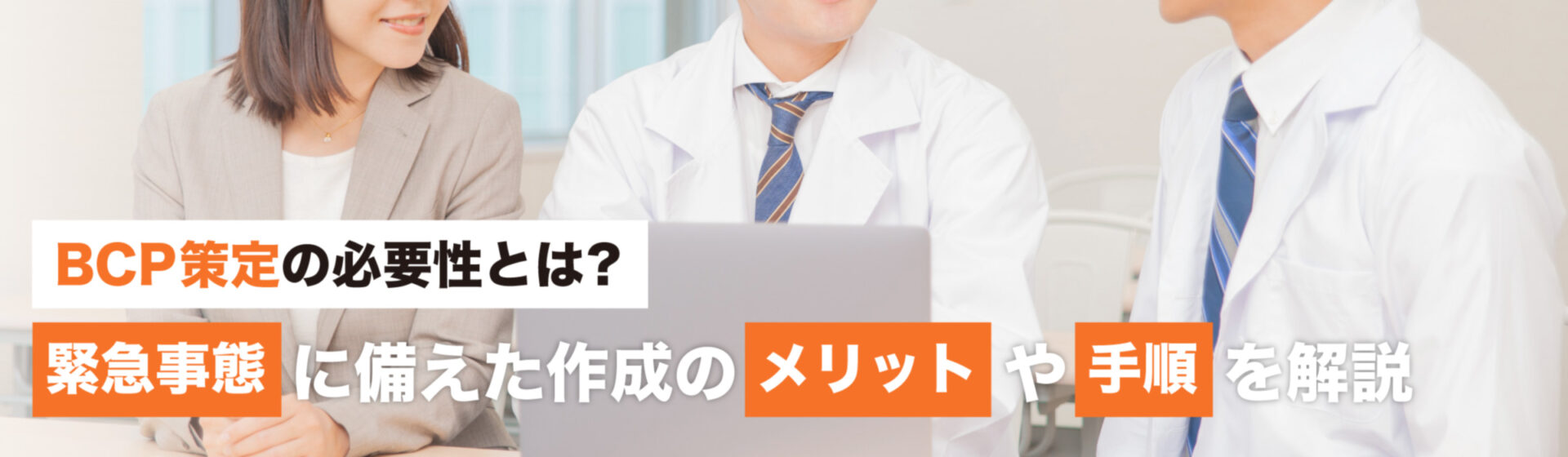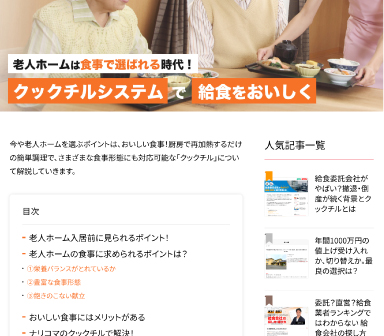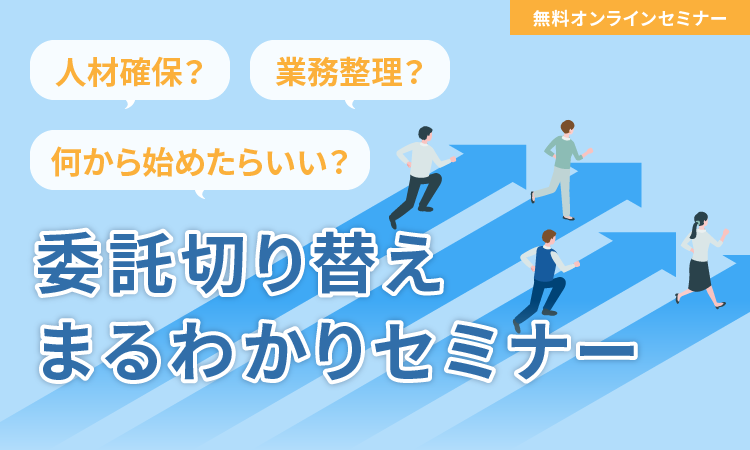BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った用語で、事業継続計画を意味する言葉です。近年に起こった大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、より必要性が認識されるようになりました。この記事では、BCPを策定する必要性や作成によるメリット、作成手順などを解説します。
目次
緊急事態に必要となるBCP

BCPは、単なる事業計画ではなく、感染症や自然災害が起きた際などの緊急事態に備えた計画であることがポイントです。不測の事態が発生しても重要な事業を中断させない、または早期復旧させるための計画がBCPです。近年に起きた大規模な自然災害や、新型コロナウイルスの感染症などにより、社会全体が大きな影響を受け、BCP策定の重要度が高まるようになりました。また、介護事業所ではBCPの策定が義務化されているため、策定は必須です。
BCPは病院や介護施設はもちろん、その他のさまざまな事業者に向けて策定が推奨されています。不測の事態をもたらす原因には、自然災害や感染症のほかにも、テロやシステム障害、大事故など多岐にわたります。こうした危機的状況が発生した時でも、できるだけ普段に近い業務環境を維持できれば、損害を最大限抑えることが可能です。
BCP策定の目的とは
BCPの大きな目的は、事業を「継続」することにあります。たとえ中断したとしても、可能な限り短い時間で事業を復旧させることが求められています。そのため、一時の備えではなく、いかなる状況でも通常行っている事業を継続できる計画が大切です。一般的な防災対策とはまた違い、継続のための具体的な計画が必要となります。
病院や介護施設のように、事業内容によっては、大規模な災害が直接利用者の生命に危険を及ぼす可能性もあります。そのため、介護施設や病院などにおいては、いかなる状況でも事業を継続することが重要で、第一に業務を中断させないようにし、中断したとしても優先業務をすぐに実施すること、可能な限り早急に復旧させることが望まれます。
自然災害や感染症のように大規模な災害が起きると、社会全体の流れが滞り大きな影響につながります。それぞれの事業者がこのような緊急事態に継続できる力を備えていれば、こうした状況でも通常の生活を維持しやすくなるでしょう。BCP策定には、こうした非常事態のダメージを防ぐ目的があり重要な役割を担っています。
BCPの策定で得られるメリット
BCPでは災害時の対応や行動を詳細に決めていくため、ある場合とない場合では災害後の状態が大きく異なることがあります。対応策がないと生命の危機や廃業に追い込まれる可能性もあるため、BCP策定のメリットは大きいでしょう。
一般的な事業全般に対してのBCPのメリットには、下記のようなポイントがあります。
- 緊急事態が起きたときに予測された速やかな行動をとることができる
- 被害を最小限に抑えて最短での復旧が期待できる
- 自社の事業を見直すきっかけとなり通常業務の改善につながる
- BCP策定が強みとなるため顧客からの信用度がアップする
病院や介護施設においては、患者や利用者の安全確保ができることとあわせて、業務を行う職員および組織自体の安全を守れることもメリットです。
BCP策定の手順をチェック

BCPにはさまざまな内容を盛り込む必要があるため、一から作り上げるのはやや大変な面があります。病院や介護施設向けのBCP策定では、厚生労働省から資料が提供されているため、これらを利用するとスムーズに策定しやすくなるでしょう。厚生労働省の提供する資料では、介護施設・災害拠点病院用・災害拠点病院以外の医療機関などに向けて、それぞれガイドラインがあります。
また、各自治体からもBCP策定に役立つ資料が提供されており、これらの情報も参考になります。BCP策定そのものに関する情報のほか、地震や水害などの被害想定などの情報も発信されているため、まずはこれらの情報集めから取り組んでみましょう。事業者全般のBCPについては、厚生労働省のページも含め、内閣府の防災情報のページにガイドラインがまとめられています。
以下では、BCPの具体的な策定手順のポイントを解説します。
1.目的を決める・体制を作る
BCPの策定では、特定の災害が起きた場合にどのような行動をとり対処していくかを考えることがポイントです。BCPには、突発的な事態に備えるため、どのような事態になっても業務を継続するという大きな目的があります。また、早期復旧をさせることも重要なため、いつまでに復旧させるかなどの時間経過ごとの目的なども定めていきましょう。緊急時には目的意識を強く持ち続けることが必要なことから、職員がイメージしやすい具体的な目的があると役立ちます。
また、BCP策定では、体制の構築も重要です。全体の意思決定者や業務の担当者など、緊急時に「誰がいつ何をするか」をあらかじめ決めておきましょう。緊急時に対処するためには組織体制が欠かせません。
あらかじめBCPを策定していても、緊急時には決められた対応策に固執せず臨機応変な対応が求められることもあります。重要視する根本の目的を明確にしておくと進むべき道がわかり、組織体制ができていればリーダーに従い行動するなどのチームワークを持って取り組むことができるでしょう。
2.緊急時のリスクを考える
緊急事態にどのような行動をとるかがBCPの要となるため、策定では考えられるリスクを全て挙げることが必要です。目的や体制などの基本方針が決まったら、次はリスクの分析や対処方法を検討していきましょう。自然災害と感染症のように、災害の種類によって行動も変わるため、リスクは状況に合わせて検討していくとわかりやすいです。介護施設用のBCPでは、自然災害と感染症でガイドラインも分かれています。
例えば自然災害の場合、事業所のある立地も大きく影響するため、ハザードマップなどを活用し想定される被害を検討することもポイントです。国土交通省から提供されているハザードマップポータルサイトでは、住所を入力するだけで、洪水や土砂災害など災害のリスク情報を調べることができます。その上で、電気や水が止まった場合の対処など、細かい部分の影響と対策を洗い出していきましょう。
3.実施する対応策の優先順位を決める
緊急事態ではさまざまなパニックも想定され、数多くのリスクが同時発生することも考えられます。限られた人員で一度に複数のリスクに対処することは難しく、時間も限られているため、何を優先して対応するかが重要です。そのため、BCP策定の段階で、リスクに対する対応策の優先順位を決めておきましょう。優先順位は、時系列や達成までの目標時間なども交えて検討しておくと役立ちます。
例えば介護事業の場合、入所・通所・訪問などの業務でどれを優先するかなども検討ポイントです。中核になっている事業や24時間365日のサービスが必要となる入所施設は、事業をストップさせないためにも優先度が高くなるでしょう。感染症の場合でも、職員の出勤率が低い場合は、通常の頻度によるシーツ交換などよりも、生命を守るための業務が最優先となります。
4.訓練・見直しを行う
BCPは作って終わりではなく、策定そのものがゴールではありません。策定したBCPが有効かどうかを確認するためにも、定期的に緊急事態に備えた研修や訓練を行いましょう。環境は日々変わっていくため、訓練の結果も踏まえ、BCPの見直しをすることも大切です。
最初から完璧なBCPを目指して一度の策定で終わりにするのではなく、随時見直しを行い、より効果的なBCPに策定していく必要があります。こうした研修や訓練もBCP策定の大切な手順の一つです。
BCP策定に役立つ支援事業
BCPには複雑な内容が盛り込まれるため、策定はある程度大変な作業になります。そのため、BCP策定に役立つさまざまな支援サービスもあります。自社で一から作るのが難しい場合は、こうした外部の支援サービスも参考にしてみてください。支援サービスでは、さまざまな事業に対応しているものもあれば、介護施設に特化しているサービスもあります。

BCP策定について学べる研修やセミナーなどもあるため、これらに参加してノウハウを学ぶのも良いでしょう。
ナリコマではBCP策定に役立つ資料配布や無料セミナーを開催しています!

ナリコマでも、これからBCPを作る施設さまに向けたBCPセミナーなどを開催しています。BCP対策に役立つ資料の配布も行っておりますので、BCP策定にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
また、ナリコマでは、災害の発生時も食事を提供するための体制が整っております。非常時にもいつもと同じように安心してお食事をとっていただけるよう、おいしい非常食もご用意しておりますので、非常食の備えもおまかせください。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
コストに関する記事一覧
-

BCPマニュアルの作成・活用 実践的な手順と注意点を徹底解説
BCPとは「Business」「 Continuity」「Plan」の頭文字を取ったもので、災害や緊急事態が発生した際に事業の中断を最小限に抑え、迅速な復旧を目指す「事業継続計画」を指します。介護施設に関しては2024年4月よりBCPの作成が義務化となり、すべての介護施設でBCPマニュアル策定が必須になりました。
医療・介護事業者にとっては、利用者の命や生活を守るためにBCPの策定が欠かせません。非常事態が起きた時でもBCPマニュアルを作成しておけば、短期間での業務復旧や多くの人々の命を守ることができます。BCPマニュアルの作成から運用、さらに病院・介護施設特有の対策について詳しく解説します。 -

BCP研修の内容とは?実施の必要性や研修サービスの選び方も解説
BCPは英語で「Business Continuity Plan」と表し、事業継続計画を意味する用語です。一般的な事業計画とは異なり、自然災害や感染症、大規模な火災、システム障害、テロ攻撃などの、危機的状況下でも重要な事業を中断させない、または早期復旧させるための計画のことです。
BCPは、策定するのはもちろんのこと、策定後の研修や訓練も重要な役割を担っています。また、研修にはBCP策定のための研修もあります。この記事では、BCP研修の必要性や内容、BCPの理解を深めるのに役立つ研修サービスの選び方などを解説します。
-

値上げは必須!介護給食の重要性と現状を詳しく解説
介護給食は、全国各地の特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで提供されている食事のこと。近年はさまざまなコストが上昇している状況にあり、介護給食の値上げも強く求められています。
本記事では、そんな介護の現場における給食をクローズアップ。給食の重要性についてお伝えするほか、調理にコストがかかる理由や厳しい現状、コスト削減方法などを解説します。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。