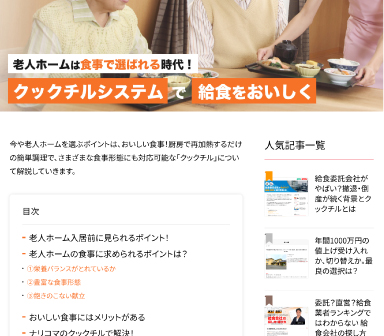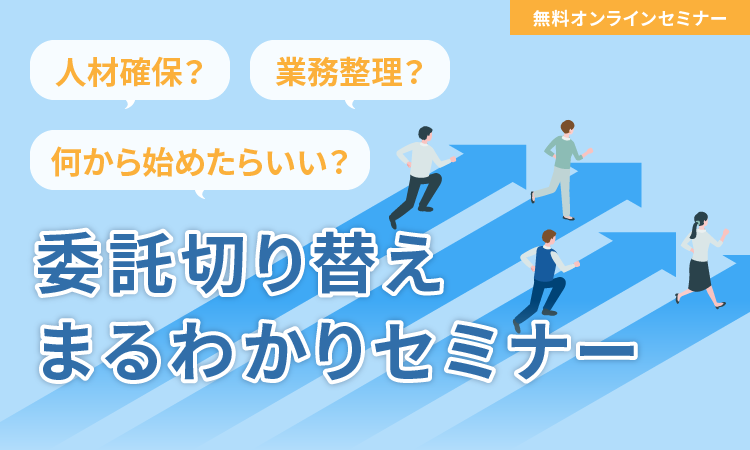セントラルキッチンは、今や飲食関連の業務に欠かせない存在となっています。導入先は飲食店やスーパーマーケット、入院設備のある病院、介護施設など多種多様。今回の記事は、そんなセントラルキッチンのシステムについてお届けします。
セントラルキッチンの仕組みと特長だけでなく、そこで調理されるクックチルに関しても詳しく解説。近年注目を浴びているセントラルキッチンの魅力をお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、導入のご参考になさってください。
目次
セントラルキッチンの仕組みと特長
まず、セントラルキッチンの仕組みと特長についてお伝えしましょう。簡潔に説明すると、セントラルキッチンは調理・加工業務を一ヵ所に集約し、調理済みの食材や料理を各所に送り出すシステム。オペレーションの効率化を意識し、計画的な生産を基本としています。
つまり、通常は細切れになってしまう複数の作業を一括して行い、さまざまな店舗や施設の調理業務をサポートしているということです。では、その具体的な仕組みと特長を見てみましょう。
セントラルキッチンの仕組み
①原材料の仕入れ
原材料の発注や入荷、検収などはセントラルキッチンの担当です。店舗や施設ごとに仕入れるよりも量が多いので、コストが削減できる場合もあります。
②食材の下処理と調理・加工
仕入れた食材は下処理をして、調理・加工の工程へと移ります。大量の食材を扱うセントラルキッチンでは、手作業以外に最新技術を搭載した調理機器を使うことも。主な調理方法はクックフリーズ、クックチル、真空調理の三つがあり、どれを採用するかは配送先の店舗や施設によって異なります。
③店舗や施設への配送
調理・加工済みの食材は配送準備に入ります。衛生面に細心の注意を払い、適温をキープしたまま店舗や施設へ配送。その後は、簡単な仕上げをするだけで提供することができます。
セントラルキッチンの特長
セントラルキッチンの主な特長としては、以下のようなポイントが挙げられます。
- 大量に仕入れることで原材料のコストが削減しやすくなる
- マニュアル化された調理・加工により品質が安定する
- 計画的な生産により食品ロスが少なく、料理のバリエーションが広がる
- 衛生管理がしやすく、食の安全性を高めることができる
- 作業を効率化することで超過勤務がなくなる
こうした基本的な仕組みや特長からお分かりいただけるように、セントラルキッチンのシステムを導入すると調理業務全般の効率化を図ることができます。人手不足やコスト高騰などに悩まされる現場では、セントラルキッチンが環境改善の鍵になるかもしれません。
セントラルキッチンで調理される 「クックチル」とは?

先ほど、セントラルキッチンの主な調理方法はクックフリーズ、クックチル、真空調理の三つがあることをお伝えしました。本項目では、そのうちの一つ、クックチルについて詳しくご紹介します。
クックチルとは、加熱調理した食材を90分以内に中心部が3℃以下になるまで急速冷却し、0℃〜3℃のチルド状態で保存する方法。専用機器や湯煎などで再加熱してから食器に盛り付け、利用者に提供します。
ここで、クックチルから派生したニュークックチルについても少し触れておきましょう。クックチルと違うのは、チルド状態のままで盛り付けまで行い、器ごと再加熱して提供する点です。ニュークックチルに対応したセントラルキッチンもあるので、ぜひ覚えておいてください。
クックチルのメリット
クックチルの大きなメリットは、チルド保存によって食中毒を防ぐ効果が高くなること。細菌が発生しやすい温度は10℃〜60℃といわれていますが、調理後の急速冷却によって、この温度帯を避けることができるのです。また、チルド状態での保存期間は製造から最大5日間ほどなので、食品ロスの防止にもなります。
また、セントラルキッチンから現場に配送された後は、再加熱と盛り付けをすれば提供可能。現場では手間や時間が削減できるため、より良い労働環境づくりにつながることもクックチルのメリットといえるでしょう。
クックチルのデメリット
上記で述べている通り、クックチルのポイントは急速冷却や再加熱。このために、専用機器を設置しなくてはなりません。セントラルキッチンのシステムを導入すれば、現場では再加熱の専用機器を購入したり、設置スペースを確保したりすることが必要になります。
さらに、揚げ物や炒め物など、一部の料理はクックチルに向いていません。提供する料理の方向性によっては、バリエーションがあまり広がらない可能性もあります。
このように、クックチルにはメリットもデメリットもあります。しかし、「食の安全性を保ちながらおいしい料理を提供する」という点ではとても優れた調理方法です。
セントラルキッチンで調理された後はどうなるの?

セントラルキッチンで調理された食材は、徹底された衛生管理の下、適温で保存・配送されます。主に使われている保存方法はチルド、冷蔵、冷凍の三通りです。それぞれ詳しく見てみましょう。
①チルド
調理後は急速冷却し、0℃〜3℃のチルド状態で保存します。保存期間は最大で5日間ほど。セントラルキッチンで盛り付けまで終わらせることが可能です。先にご紹介したクックチルがこれに当たり、病院や介護施設などでよく使われています。
②冷蔵
調理後は10℃以下の冷蔵庫で保存します。チルドと同じく、セントラルキッチンで盛り付けまで終わらせることが可能です。消費期限が短くなる傾向にあり、配送頻度は高め。キッチンカーや飲食店でよく使われています。
③冷凍
調理後は急速冷凍し、-18℃以下の冷凍庫で保存します。ニーズに合わせ、大量にまとめて冷凍するタンク式、小分けにされたパック式などを選択。長期保存ができるため、遠方まで配送可能です。全国各地にチェーン展開するファミリーレストランや居酒屋などでよく使われています。
外食、給食で注目されるセントラルキッチン方式
冒頭でもお伝えしましたが、セントラルキッチンは特に注目度が高くなっているシステムです。近年では、全国展開するファミリーレストランがコスト削減のため各地にセントラルキッチンを設置したり、大規模な総合病院が外部のセントラルキッチンに給食業務を委託したりといったケースが多く見られます。
このほか、給食業務の委託を受けている企業がセントラルキッチンを活用して事業所の負担を減らした例も。外食や給食以外のところでは、高級スーパーマーケットが自社の製造力を上げるためにセントラルキッチンを拡大し、プライベートブランド商品を充実させたことも話題になりました。
セントラルキッチンは、全体的にはとてもシンプルな仕組みです。しかし、変化に富んだニーズにもしっかりと応えられる幅広い選択肢があります。まさにこれが、さまざまな方面から注目を集め、導入が進められている理由ではないでしょうか。セントラルキッチンは、将来的にもまだまだ成長を続けていくでしょう。
まとめ
今回の記事はセントラルキッチンの仕組みと特長をテーマに、調理方法のひとつであるクックチルの詳細や食材を調理した後の流れなども併せてお伝えしました。
各方面から注目されているセントラルキッチンは、病院食や介護食を提供するナリコマグループでも稼働中。コストを抑えながら高品質の料理をお出しできるよう、データ活用と最新技術を取り入れ、より良い調理方法やサポート体制を探求しています。セントラルキッチンのシステムを導入される際には、どうぞ選択肢の一つとしてご検討ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

医療・介護施設のBCP策定ガイド!安心安全な施設運営のために
地震や台風などの自然災害は、いつどこで発生するかわかりません。特に、医療や介護を支える病院や施設においては、災害が発生してもその役割を止めることなく継続する必要があります。
停電や断水、物流の停止などによって、通常の施設運営が困難になるケースも少なくありません。こうした緊急時に備えるために欠かせないのがBCP(事業継続計画)です。BCPとは、災害や緊急事態が発生した場合でも、業務を継続・早期復旧させるための計画で、特に命を預かる医療・介護施設にとってBCPの策定はとても重要になってきます。
今回は、災害時における医療・介護施設が直面する課題や対策方法などについて詳しく解説していきます。いざという時に備え、今からできる準備を一緒に考えていきましょう。
-

病院給食が約25年ぶりに値上げ!費用算出方法や物価高騰への対策を解説
病院給食は、その名の通り、主に入院患者さんに提供されています。価格は長らく据え置かれてきましたが、2024年6月1日に値上げが行われたことで注目を集めました。今回の記事は、この「病院給食の値上げ」をテーマにお届けします。
病院における給食の重要性や、値上げに至った背景などを詳しく解説。近年さまざまなところで影響を及ぼしている物価高騰への対策についてもまとめてみました。ぜひ最後までお読みください。
-

給食業界における最大の課題!コスト高騰化を乗り切る解決策とは
近年は数多くの商品やサービスの値上げラッシュが続いており、多種多様な業界はもちろん、消費者にも大きな影響を及ぼしています。食品や日用品の買い出しで「高くなった」と実感している方は少なくないでしょう。値上げの主な理由は、生産費や人件費といった各種コストの高騰化。この件は、給食業界においても最大の課題として解決が求められています。
本記事では、今や身近なテーマともいえるコスト高騰化について解説。詳しい要因を見ながら、給食を必要としている施設の現状や具体的な解決策などをお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

医療・介護施設のBCP策定ガイド!安心安全な施設運営のために
地震や台風などの自然災害は、いつどこで発生するかわかりません。特に、医療や介護を支える病院や施設においては、災害が発生してもその役割を止めることなく継続する必要があります。
停電や断水、物流の停止などによって、通常の施設運営が困難になるケースも少なくありません。こうした緊急時に備えるために欠かせないのがBCP(事業継続計画)です。BCPとは、災害や緊急事態が発生した場合でも、業務を継続・早期復旧させるための計画で、特に命を預かる医療・介護施設にとってBCPの策定はとても重要になってきます。
今回は、災害時における医療・介護施設が直面する課題や対策方法などについて詳しく解説していきます。いざという時に備え、今からできる準備を一緒に考えていきましょう。
-

値上げは必須!介護給食の重要性と現状を詳しく解説
介護給食は、全国各地の特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで提供されている食事のこと。近年はさまざまなコストが上昇している状況にあり、介護給食の値上げも強く求められています。
本記事では、そんな介護の現場における給食をクローズアップ。給食の重要性についてお伝えするほか、調理にコストがかかる理由や厳しい現状、コスト削減方法などを解説します。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

給食管理システムを選ぶコツ!病院や介護施設におすすめ
病院で給食を口にするのは、主に病気やケガで入院中の方々です。そのため、病院における栄養管理には大きな役割があります。少しでも早く回復するためには、投薬などの治療やリハビリに加え、栄養バランスのとれた食事が欠かせないでしょう。
ただ、栄養管理は病院に限らず、介護施設や保育園などでも重要な業務です。本記事は、さまざまな施設で欠かせない給食の栄養管理に注目。現場で重宝される給食管理システムの詳細、給食業務に携わる栄養士・管理栄養士が重視するポイントなどをまとめてお伝えします。ぜひ、システム導入のご参考になさってください。