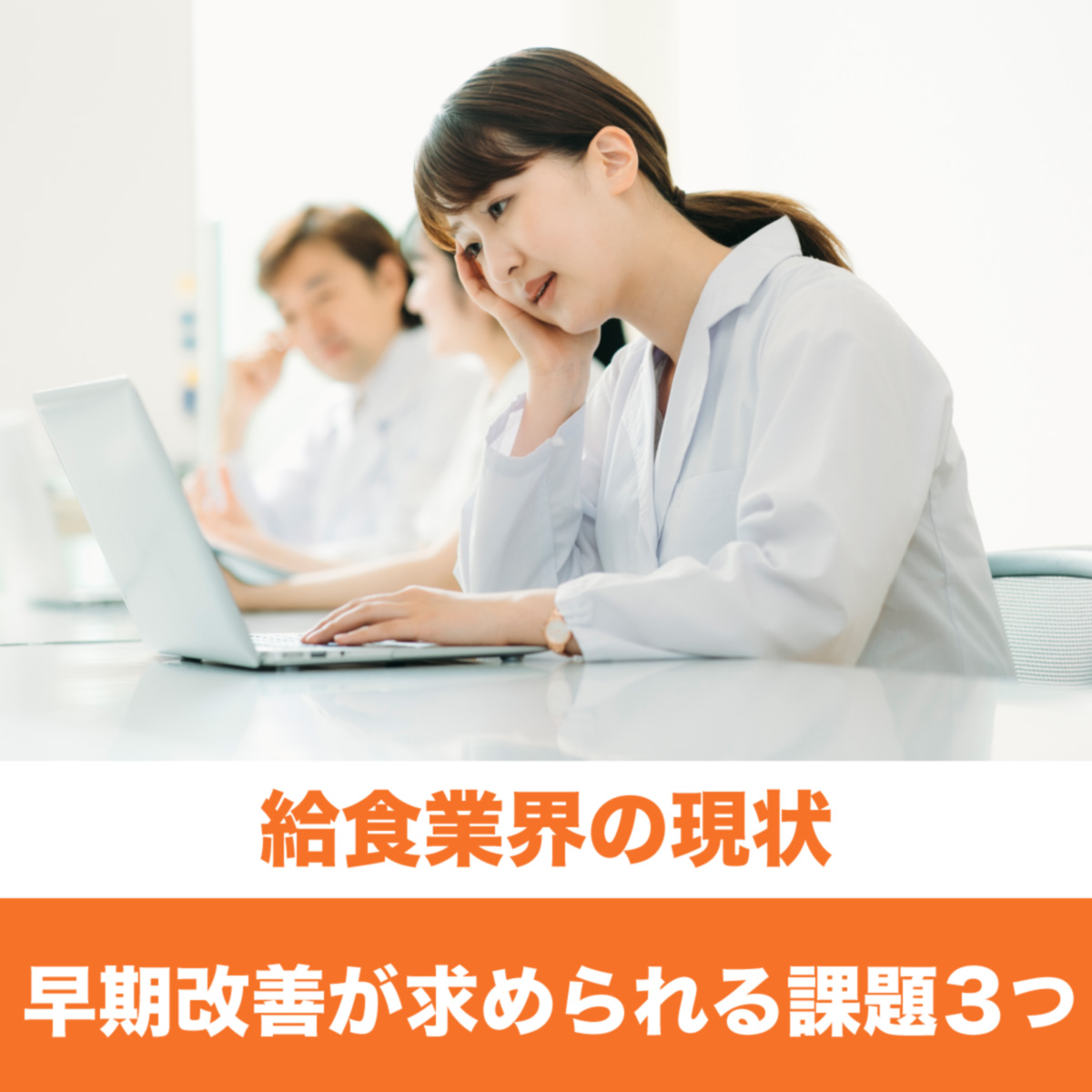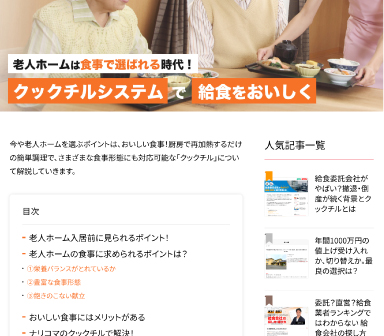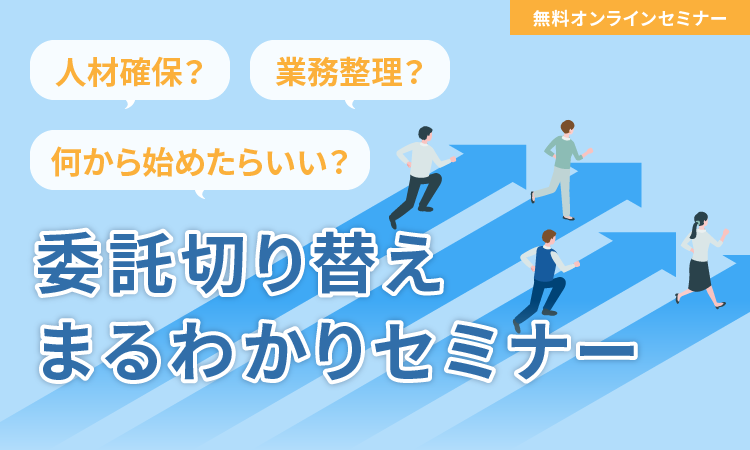給食は保育所や学校、病院、介護・福祉施設、社員食堂など、いろいろな場所で人々のお腹を満たし、健康を支えています。しかし、その給食を提供する側に目を向けると、いくつかの課題が浮き彫りに。近年、給食業界は厳しい状況にあると指摘されており、早めの対策が必要といわれているのです。
本記事では、給食業界が抱える複数の課題から、特に重視すべき3つをピックアップ。課題の内容とともに、その要因や改善のポイントも詳しくお伝えします。
目次
給食の役割と重要性

給食の定義を端的に表すと、「特定の集団に対して提供される食事」のこと。まずは、社会にとって給食業界がどのような存在なのか考えてみましょう。本項目では、主な施設ごとに給食の役割を解説します。
保育所や学校
幼児から小学生、中学生ぐらいまでを対象とした給食は、成長期に必要な栄養をきちんと摂取するという目的があります。食育としての役割も大きく、他人と食事をすることで社会性やコミュニケーション能力を高めたり、食事のマナーを身に付けたりする機会になっているのです。また、季節や地域の食文化を知るきっかけとしても最適。食料生産の仕組みや重要性を理解し、「食料は自然から与えてもらう貴重なもの」「食べ物を粗末に扱ってはいけない」「生産者の方々への感謝を忘れずに」といった道徳的思考の育成に必要ともいわれています。
病院などの医療施設
病院などで提供される給食は、医療の一環として考えられています。担当医師や管理栄養士が患者一人ひとりの状態に合わせて食事療法の方針を決め、それに従ったメニューを提供。早期回復をサポートすることが主な役割で、患者の病状などが変われば、食事療法の方針も変更されます。場合によっては、退院後の食生活や栄養管理の指導を行うことがあります。
介護・福祉施設
高齢者が多い介護・福祉施設の場合、給食は毎日の生きがいとしての役割が強くなります。もちろん、健康維持のために十分な栄養をとったり、季節感や生活リズムを意識したりする手段としても有効です。周囲と関わり、社会参加ができることも重要な意味があります。また、嚥下機能が低下した高齢者には、ソフト食やミキサー食、ゼリー食といったバリエーションのある介護食を提供。「食べることが楽しい」と思ってもらえるような工夫も必要です。
社員食堂
“社食”と略されることも多い社員食堂は、企業が提供する福利厚生の一つです。ここでの給食が持つ役割は、社員の健康をサポートして生産性を上げることと、社員同士がコミュニケーションをとる場所を与えること。対外的なところでは、企業のイメージを向上させる狙いもあります。
以上のことからわかるように、社会のさまざまな場所と結びついているのが給食業界です。一定数の需要があるからこそ、これからお伝えする課題を解決し、安定的な供給体制を整えなくてはなりません。
給食業界の課題①コストが高騰しても続けなくてはならない
近年はコスト高騰化が進んでおり、給食業界にも非常に大きな打撃を与えています。2020年〜2021年ごろは、新型コロナウイルスの感染拡大によって世界全体で社会情勢が変化。需要と供給のバランスが崩れたことから、各種コストが少しずつ上がり始めました。

2022年2月にはロシアがウクライナ侵攻を開始。小麦などの食料が値上がりし、エネルギー資源の供給ルートも不安定になったのです。そこに追い打ちをかけるように、2023年10月にはパレスチナ問題によって中東地域の情勢が悪化。エネルギー資源の価格が落ち着く可能性は一段と低くなりました。
現在はドル高/円安の傾向が強まっており、輸入品を取り扱う企業側も値上げせざるを得なくなっています。加えて、日本国内では猛暑や降水量不足といった天候不順、自然災害なども頻発。直接的な影響を受けてしまう米や野菜などの農作物は、例年と比べて大幅に高騰しています。
こうした背景があり、給食にかかるコストは軒並み上昇しているのです。しかし、コスト面でかなり厳しい状況に置かれているにもかかわらず、給食の提供は簡単に止められません。それは、子どもや高齢者、病人に至るまで、多くの人々にとって極めて重要な「食」を担っているから。給食は値上げが制限される競売入札も多く、コスト高騰の分を価格に反映させにくいのです。そのため、現場では可能な限りコストを削減する必要があります。
給食業界の課題②人手不足に陥ってしまう現場が多い

慢性的な人手不足は、給食業界で以前から指摘されている課題の一つ。その要因となっているのは、業務と給与のアンバランスです。例えば、一日三食をきっちり提供しなくてはならない病院などでは、公共交通機関も動いていない早朝に出勤したり、当日の片付けや翌日の仕込みをするために深夜まで残業したりするケースがあります。そういった勤務体制で働き続ける従業員は、心身に大きな負担がかかりがち。継続的な勤務がつらくなり、辞めてしまう従業員も少なくないのです。
現場は少ない人数で通常通りに業務をこなすことになるので、疲労がたまって労働効率も下がり、結果的に悪循環が生まれてしまいます。課題①で述べたように、給食は値上げが難しいという特徴があります。人件費が十分に確保できなくなり、「業務はつらいのに給与は低水準」という状況になってしまうのも当然かもしれません。
求人ボックス給料ナビの統計データ(2024年10月30日時点)にある正社員の平均年収を参照すると、給食調理は321万円、栄養士は336万円、管理栄養士は326万円とあります。国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」には給与所得者全体の平均年収が460万円とあるので、給食業界の給与水準は低いといえます。慢性的な人手不足を解消するには、勤務体制に加え、給与面も改善しなくてはならないでしょう。
給食業界の課題③労働環境が悪くなりやすい
課題②でも触れていますが、給食の現場は早朝・深夜に勤務しなければならないケースがあるほか、人手不足で業務が滞りがち。その点を含め、給食業界は労働環境があまり良くない傾向にあるといわれています。
というのも、給食は一度に大量の食材を仕込み、調理するのが基本。調理器具の洗浄などもあるため、業務内容は必然的に重労働が多くなります。早朝・深夜の勤務がなかったとしても、厨房内で働く以上、体力勝負になる部分も大きいでしょう。

そして、調理業務以外にも食材の発注・在庫管理、厨房の衛生管理、各種帳票の作成など幅広い業務があります。特に事務関連については電子化があまり進んでいない現場もあり、作業効率が上がらないケースもあるようです。
また、一人で黙々と作業するのではなく、仲間と連携してチームで業務をこなすのも特徴。給食の現場には女性従業員が多いため、そういった環境でもコミュニケーションが円滑にいくかどうかが重要です。女性が多い職場や人との会話が苦手な人の場合、強いストレスを感じやすい環境だといえるでしょう。
さらに、専門職の栄養士や管理栄養士は上記以外の点でも苦労が多いようです。勤務先の施設規模があまり大きくなければ、配置人数はたいてい一人。業務上の悩みも共有・相談する相手がいなかったり、立場が違う従業員同士の間で板挟みになったりすることがあるといいます。
このような労働環境を改善するには、業務フローや勤務体制の見直しだけでなく、効率化のツール、外部サポートサービスの導入なども必要になるかもしれません。
ナリコマが課題の解決をお手伝いします

ナリコマでは、本記事でお伝えした給食業界の課題解決に向け、さまざまなご提案をしております。自慢の献立サービスは、病院や介護・福祉施設向け。少人数で対応しやすいクックチルやニュークックチルを活用し、全体的なコスト削減に貢献できた事例もあります。導入後は、事務作業に便利なオリジナルシステム、教育・研修といったサポートも充実。厨房運営でお悩みの際には、ぜひナリコマにご相談ください。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

BCPマニュアルの作成・活用 実践的な手順と注意点を徹底解説
BCPとは「Business」「 Continuity」「Plan」の頭文字を取ったもので、災害や緊急事態が発生した際に事業の中断を最小限に抑え、迅速な復旧を目指す「事業継続計画」を指します。介護施設に関しては2024年4月よりBCPの作成が義務化となり、すべての介護施設でBCPマニュアル策定が必須になりました。
医療・介護事業者にとっては、利用者の命や生活を守るためにBCPの策定が欠かせません。非常事態が起きた時でもBCPマニュアルを作成しておけば、短期間での業務復旧や多くの人々の命を守ることができます。BCPマニュアルの作成から運用、さらに病院・介護施設特有の対策について詳しく解説します。 -

今後どうなる?給食業界の課題と将来性を詳しく解説
給食は、保育所や学校、病院、老人ホームといったさまざまな施設で提供されています。施設を利用する人々にとって、給食は健やかな生活を送るために欠かせないものでしょう。ところが、その一方で、現在の給食業界は大きな課題をいくつも抱えています。
今回の記事で取り上げるテーマは、給食業界の将来性。近年における業界の動向や解決すべき課題を挙げ、今後の展望について解説します。ぜひ、最後までお読みになってください。
-

特養の給食委託。選び方のポイントと成功事例を紹介!
現在、給食委託は病院や学校などをはじめとする多くの施設で利用されています。
特別養護老人ホーム(以下、特養)もそのうちの一つで、超高齢社会が進む近年は需要が増加。今回の記事は、そんな特養の給食委託についてお届けします。
特養に最適な給食委託会社の選び方をポイント別に解説。
後半では、給食委託以外の選択肢についてもお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、ご参考になさってください。
コストに関する記事一覧
-

給食委託会社との良好な付き合い方
給食業務における人手不足やコストなどの悩みを抱えているときに、給食委託会社の利用で解決できることがあります。しかし、場合によっては新たな問題が生じることもあるのが難点です。メリットやデメリットもあり、委託というスタイルによって今までできていたことが簡単にできなくなることもあるでしょう。
給食委託会社の利用によるデメリットでは、関係の構築に時間がかかることがしばしば挙げられます。これは単にやり取りに時間がかかるだけでなく、いくつかのトラブルが生じて、解決するまでの時間も含まれるでしょう。給食委託会社と依頼する側のトラブルは、残念ながらさまざまにあり、給食委託会社と良好な関係を構築することは難しく複雑であることもわかります。
今回は、給食委託会社を利用する際の関係構築の重要性と共に、どうすれば良好な付き合い方ができるのかを解説します。トラブルを防ぐためのポイントを押さえた関わり方や、トラブルが起きた際の早急な解決ができるように、給食委託会社の利用の際には改めて意識しておきましょう。 -

ちゃんと食べていても体重が減っていく?高齢者の食事は少量高栄養で!
高齢者になると健康上の問題が目立つようになります。当然個人差はありますが、健康状態を左右する食事の困りごとはいち早く解決したいものでしょう。「若い頃と同じように食べられなくなった」「食欲がなくなってきた」といった声は、いつの時代も聞こえてきます。
本記事で取り上げるのは、しっかり食べているのに体重が減るという「やせ(低体重)」の問題。高齢者の体重減少を引き起こす理由や具体的な原因を解説し、「やせ」の危険性についてもお伝えします。
また、そんな高齢者の食生活をサポートする少量高栄養の介護食・給食についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。 -

これから採用すべきは「未経験者」!?厨房で即戦力を育てるヒント
病院や介護施設などでは、厨房の人手不足の悩みが深刻化しています。問題が解決しない背景には、募集をかけても調理員の応募がない、という実態もあるようです。未経験でも勤務可能な調理員は一見応募のハードルが低いように思えますが、なぜ応募が少ないのでしょうか?
この記事では、調理員が集まらない理由から、未経験者にとって厨房業務がつらく感じる理由、未経験者が活躍できる厨房にするための解決策とクックチルの特長について解説します。