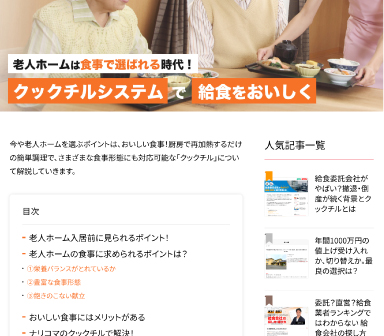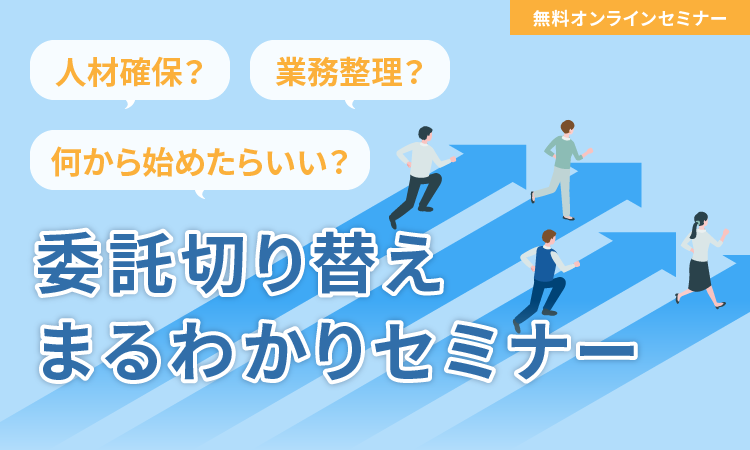たくさんの高齢者を預かる介護施設や病院では、介護食の存在が欠かせません。毎日の食事で栄養をとることは大切ですが、高齢者は嚥下機能の程度に個人差があることも多々。そういった状況に対応できるのが介護食です。
ミキサー食をはじめ、さまざまな種類を取りそろえているのが介護食の特徴。本記事はミキサー食とペースト食の違い、ムース食とソフト食の違いなど、介護食について詳しくお届けします。ミキサー食の基本的な作り方や注意点もまとめてお伝えしますので、ぜひお役立てください。
目次
介護食の種類には何がある?

介護食を導入する大きな目的は、高齢者の誤嚥を防ぐこと。誰しも高齢になれば咀嚼する力は衰えていき、食べ物を食道や気管に詰まらせる恐れがあります。
だからこそ、介護施設や病院で介護食が重宝されるのです。まずは、介護食の主な種類とそれぞれの特徴を見てみましょう。
介護食の種類①きざみ食
きざみ食は、食材を細かく刻んだ食事です。咀嚼する力が弱ってきた方に向いています。食材は約5mm〜2cmに刻むので、介護食でありながら、普通食に近い見た目と食感に仕上がります。
固形物を食べる楽しみがある一方、飲み込む力が弱い方の場合は誤嚥の可能性がやや高くなるので注意が必要です。
介護食の種類②ソフト食(軟菜食)
ソフト食は軟菜食とも呼ばれ、食材を歯茎や舌で潰せるくらいにやわらかくした食事です。食材をミキサーにかけて固め直す場合もあります。咀嚼する力と飲み込む力が弱ってきて、きざみ食では難しい方におすすめです。
食感は異なるものの、見た目は普通食に近くなります。細かく刻む手間はありませんが、食材ごとの丁寧な調理が必要です。
介護食の種類③ミキサー食
ミキサー食は、食材をなめらかなポタージュ状にした食事です。ほぼ噛まずに飲み込めるため、きざみ食やソフト食が難しい方に向いています。
ミキサーで調理できる食材を使い、水分が多い場合にはとろみをつけるのが一般的です。普通食と比べて見た目や食感が大きく変わってしまうので、食欲減退につながることも。攪拌前の料理を見せて、どんなものか説明してから食べてもらうと良いかもしれません。
介護食の種類④ゼリー食
ゼリー食は、ミキサーにかけた食材をゼラチンや寒天などで固めた食事です。ミキサー食よりもまとまっており、するりと飲み込めるため、咀嚼する力がかなり弱ってしまった方に向いています。
見た目や食感が普通食とはまったく違うので、型抜きしてもともとの食材に似せるなど、おいしそうに見せる工夫が必要です。
介護食の種類⑤流動食
流動食は、固形物を濾して液体状にした食事です。咀嚼する力と飲み込む力に加え、消化機能も弱っている方に向いています。メニューの一例は具材なしの汁物、重湯(お粥の上澄み)、ヨーグルトなどです。
このように、介護食には多彩なバリエーションがあり、いろいろな方の食事に対応できます。続いて、ミキサー食とペースト食の違いについて解説しましょう。
ミキサー食とペースト食の違いは?
ペースト食はミキサー食とよく似ています。場合によっては同一の種類としてみなされることもあるでしょう。では、ミキサー食とペースト食の違いを細かくみていきます。
ペースト食とは、ミキサーなどを使って食材をしっかりとすり潰した食事のこと。ミキサー食も食材をミキサーにかけてすり潰すので、基本的な部分では同じと考えられます。この二つの大きな違いは、食事に含まれる水分量です。なめらかなポタージュ状にするミキサー食と比べて、ペースト食は水分量がかなり少なめ。粘度があるため、ミキサー食よりも誤嚥しにくいとされています。
ただ、きざみ食やソフト食とは異なり、見た目や食感が本来の食材とかけ離れてしまう点はミキサー食と同じです。今は優れた栄養補助食品やサプリメントもありますが、やはり食事から栄養をとることのほうが大切。きちんと食べてもらうためにも、彩りが良くなるよう食材ごとに分けて盛り付けるなど、食欲を刺激するような工夫が求められます。
ムース食とソフト食の違いは?
ミキサー食とペースト食の違いに続いて、ムース食とソフト食もまた、同一の種類としてみなされることがあります。では、二つの違いについて詳しくみてみましょう。
介護食の種類を挙げた項目では、ソフト食について「食材をミキサーにかけて固め直す場合もある」とお伝えしました。まさにこれがムース食の基本となります。つまり、ムース食はソフト食の一つと考えられるのです。きざみ食やミキサー食とは違い、いろいろな形に固められるのも大きなメリット。調理の手間はかかりますが、おいしそうな見た目に仕上げることができます。
ムース食は咀嚼する力や飲み込む力が弱っているだけでなく、食べ物を口の中でうまくまとめられない方にもおすすめ。ほとんど噛めない方はミキサー食やペースト食にしたほうが良いかもしれませんが、少しでも咀嚼できるのであれば、ムース食で様子をみるのも選択肢の一つになります。
ミキサー食の作り方と注意点

ミキサー食は一般のご家庭でも手軽に調理できます。本項目ではミキサー食の基本的な作り方と注意点をまとめたので、ご参考になさってください。
ミキサー食の作り方
ミキサー食を作るときの基本工程は非常にシンプルで、その名の通り、食材をミキサーに入れて攪拌すること。一般的なレシピでは、攪拌が終わった食材を水や出汁で薄めて仕上げます。
ミキサー食の注意点①攪拌しやすい食材を使う
ミキサーでの調理は、向いている食材と向いていない食材があります。ほうれん草や小松菜といった葉物野菜の穂先、でんぷん質の多いイモ類や豆類などはミキサーにかけやすい食材です。料理でいうと、肉じゃがやシチューなどの煮物も攪拌しやすいものに含まれます。反対に、弾力のあるキノコ類やこんにゃく、繊維質が多い野菜、脂肪分が少ない魚肉や赤身肉はミキサーでの調理におすすめできません。
ミキサー食の注意点②粘度と水分量は嚥下機能に合わせる
ミキサー食とペースト食の違いとして挙げた粘度や水分量も、注意すべきポイントです。水分が多いと誤嚥が起きやすくなりますが、粘り気が強すぎると喉に張り付いてしまいます。
とろみをつける場合は片栗粉や葛を使いますが、市販のソースやタレ、ドレッシングなどで和えるのもおすすめ。食べる方の嚥下機能に合わせ、程よい加減に調整しましょう。
ミキサー食の注意点③彩りと味付けにこだわる
きざみ食やソフト食は普通食に近い見た目ですが、ミキサー食はドロドロの状態です。見た目の悪さは食欲減退につながります。おいしそうに見せるため、彩りや味付けのバリエーションが増えるように工夫しましょう。
ナリコマのミキサー食の特長
介護食の種類、ミキサー食とペースト食の違いなどについて詳しくお伝えしましたが、いかがでしたか?
では最後に、ナリコマグループがお届けするミキサー食をご紹介しましょう。
ナリコマでは介護施設や病院向けに、365日楽しめる献立サービスをご用意しています。普通食・ソフト食・ミキサー食・ゼリー食の4形態がそろっているので、食べる方の嚥下機能に合わせて選択可能。なかでも、ミキサー食は食材ごとの味や香りを引き出せるよう、特殊な機器で調理するというこだわりがあります。
一般的なミキサー食は水や出汁を使って薄めますが、ナリコマのミキサー食にはその工程がありません。そのため、少量でも十分な栄養がとれるのです。嚥下機能に不安がある方はもちろん、食事量があまり多くない方にも最適。栄養たっぷりのおいしいミキサー食をお探しの際には、ぜひナリコマの献立サービスもご検討ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

医療・介護施設のBCP策定ガイド!安心安全な施設運営のために
地震や台風などの自然災害は、いつどこで発生するかわかりません。特に、医療や介護を支える病院や施設においては、災害が発生してもその役割を止めることなく継続する必要があります。
停電や断水、物流の停止などによって、通常の施設運営が困難になるケースも少なくありません。こうした緊急時に備えるために欠かせないのがBCP(事業継続計画)です。BCPとは、災害や緊急事態が発生した場合でも、業務を継続・早期復旧させるための計画で、特に命を預かる医療・介護施設にとってBCPの策定はとても重要になってきます。
今回は、災害時における医療・介護施設が直面する課題や対策方法などについて詳しく解説していきます。いざという時に備え、今からできる準備を一緒に考えていきましょう。
-

病院給食が約25年ぶりに値上げ!費用算出方法や物価高騰への対策を解説
病院給食は、その名の通り、主に入院患者さんに提供されています。価格は長らく据え置かれてきましたが、2024年6月1日に値上げが行われたことで注目を集めました。今回の記事は、この「病院給食の値上げ」をテーマにお届けします。
病院における給食の重要性や、値上げに至った背景などを詳しく解説。近年さまざまなところで影響を及ぼしている物価高騰への対策についてもまとめてみました。ぜひ最後までお読みください。
-

給食業界における最大の課題!コスト高騰化を乗り切る解決策とは
近年は数多くの商品やサービスの値上げラッシュが続いており、多種多様な業界はもちろん、消費者にも大きな影響を及ぼしています。食品や日用品の買い出しで「高くなった」と実感している方は少なくないでしょう。値上げの主な理由は、生産費や人件費といった各種コストの高騰化。この件は、給食業界においても最大の課題として解決が求められています。
本記事では、今や身近なテーマともいえるコスト高騰化について解説。詳しい要因を見ながら、給食を必要としている施設の現状や具体的な解決策などをお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。