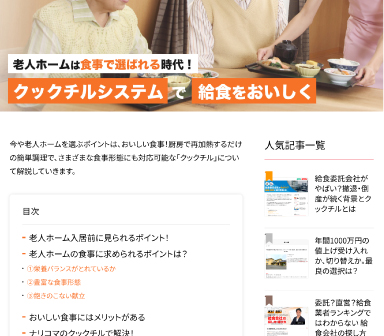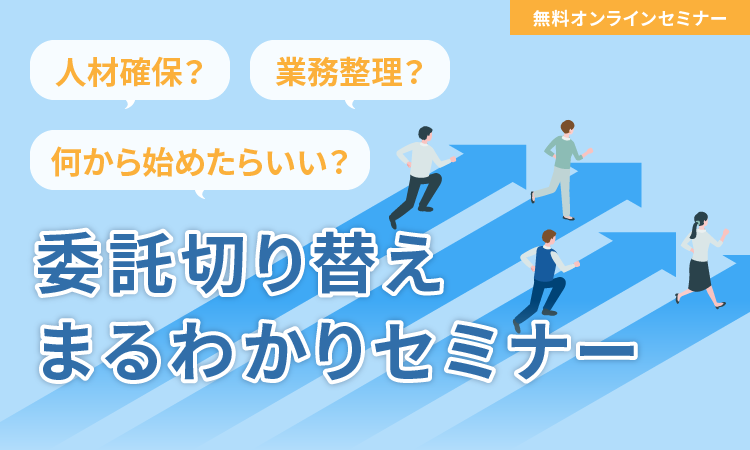今もなお、ネガティブなイメージが付きまとう病院食。病院食は味気ないというイメージはもう昔の話です。現在では、患者の治療や回復を支えるため、栄養バランスだけでなく、おいしさや見た目に配慮した食事が提供されています。進化を遂げるおいしい病院食、その裏にある技術や取り組みに迫ります。
目次
病院の食事は治療の一環

病院食は単なる栄養摂取の手段にとどまらず、治療効果の向上や回復を早めるなどの役割を果たしています。適切な栄養管理を行うことで患者の入院期間を短縮する効果も期待できるでしょう。
病院食は大まかに「一般食」と「特別治療食」の2つに分けられます。「一般食」は特に制限のない食事ですが、患者の病態に合わせて「特別治療食」が提供されています。たとえば、糖尿病の患者にはエネルギーコントロール食、腎疾患の患者にはたんぱく制限食や減塩食など、それぞれの病態に合った特別な食事となります。
こうして食事療法を取り入れることで、病気の改善だけでなく合併症の予防にもつながるため、病院食は治療の一環として大きな役割を担っているのです。
病院食はおいしくない?イメージが変わる時代へ
かつての病院食といえば、「味が薄い」「おいしくない」といったイメージが一般的でした。病院食の歴史を振り返ると、長い間「治療のための食事」という実用的な側面が重視されてきました。
1950年に策定された完全給食制度を始まりとして、病院食が提供されるようになりましたが、患者の疾患に合わせた最低限の栄養補給を目的としており、味や見た目の配慮はほとんどありませんでした。
しかし、栄養学の発展とともに、患者の快適さや満足度が治療に与える影響が注目されるようになり、病院食も徐々に変化していきました。1970年代以降、日本では「医療の一環としての食事」という考え方が広まり、栄養だけでなく、患者の好みにも配慮した食事が提供されるようになったのです。
こうして近年では、調理技術や保存技術の進化により、高品質で多様なメニューが提供可能となり、病院食はより患者中心のものへと進化を遂げています。現在では、多くの病院が暖かい料理を暖かいまま、冷たい料理を冷たいまま提供する取り組みを進めています。
食形態が変わってもおいしい病院食の登場
厚生労働省が行った「令和5年(2023)患者調査」では、入院総数が1135.3千人に対して65歳以上の入院患者は887.2千人と大きな割合を占めていることがわかりました。高齢になってくると、筋力や活動量の低下から嚥下機能も低下する傾向にありますが、食形態も嚥下機能に併せて変更が必要になってきます。
ミキサーで細かくすりつぶしたペースト食など、食材に水分を加えることで味が薄くなってしまったり、見た目や食感も普通食とはだいぶ変わってしまいます。
また、入院患者の低栄養に関する調査によると、入院中の65歳以上の高齢者では16人に1人が低栄養の状態であるといった結果が出ています。低栄養は嚥下機能の低下や、食事摂取量の低下が原因とされており、低栄養が続くと免疫力が低下し、床擦れやケガ、傷の回復がしにくい状態になってしまいます。

身体機能に合わせた食事形態には、食べやすく細かく刻んだ「刻み食」や、咀嚼力が低い人のために、歯茎でつぶせるほどやわらかい「ムース食」「ペースト食」などがあります。
病院の給食部門の課題として、人手不足が挙げられますが、これらの食事は一般食と違って加工するのに時間も手間もかかってしまいます。人手不足の中、工数のかかる加工作業を行うのはとても大変なことです。
昨今では、加熱調理した食事を急速冷凍したクックチルシステムを活用する病院も増えてきています。クックチルシステムなら、異なる食形態の場合でも加工済の状態で配送されるため、少ない人数でも問題なく対応できるのです。また、特殊な調理機械を使用することで、味わいや栄養価を損なわずにおいしく調理できるのもクックチルシステムの魅力です。
病院食の品質向上にむけて
病院食については、味や栄養面での満足度が低いことが課題として挙げられることもあります。日本臨床栄養代謝学会主催の「患者さんのための見た目にも美味しい病院食コンテスト」など、病院食の質の向上と患者満足度の向上を目指す取り組みも行われるようになりました。
患者さまに「おいしい病院食」を提供するため、さまざまな病院が試行錯誤していることでしょう。病院食の品質向上のために、具体的にどのような取り組みが必要なのでしょうか。
品質を安定させる
作る人によって味が変わってしまうと、おいしいとはなかなか感じなくなってしまうものです。毎日安定した品質、おいしさを届けることも大切です。調理方法や味付けの工夫も、塩分や脂肪分を抑えた調理法を取り入れながらも、旨味や風味をしっかりと引き出し、毎日安定した品質で提供できるよう改善が必要です。
患者の食事に対する意見を聞く
患者の食事に対する意見や感想を反映させることで、より良い病院食の提供が可能になります。そのためには、スタッフとのコミュニケーションを大切にし、小さなことでも共有しあえる関係を築くことが大切です。
視覚的な魅力を高める
おいしい病院食には、見た目の美しさも重要です。彩り豊かな食事は、食欲を引き出し、患者にとっても食事の時間が楽しみとなります。見た目にもおいしい病院食を実践している2つの事例を紹介します。

病院食の品質改善の実践例
九州のある病院では、患者満足度調査の結果が低いことを受け、「食事改善プロジェクト」を立ち上げて病院食の課題に向き合い、改善を目指す試みを行っています。お正月などの行事食はいつもの食器とは違った折詰で提供するなど、盛り付けや食器を変えて提供することで、満足度の向上につながったケースもあります。
また、山口県のとある病院では直営給食にこだわり、季節の食材を活用したり、食欲をそそる明るい色の食材を多く使って彩りを鮮やかに仕上げています。四季折々の行事食を提供し、一言メモを添えるなど視覚的な楽しさを加える取り組みを行っています。
おいしさを追及したナリコマのクックチル
病院食の「おいしさ」をもっと追及したいけれど、人手不足で時間や人員をかけられないといったお悩みを抱えている病院も少なくないでしょう。
そんなお悩みを解決するのがナリコマのクックチルシステムです。このシステムは、病院食の品質向上に革命をもたらす技術として、多くの医療機関で導入されています。ナリコマのクックチルシステムがどのように「おいしい病院食」を実現しているのか、詳しく見ていきましょう。
クックチルとは?
クックチルとは加熱調理した食材を急速冷凍し、0℃〜3℃のチルド状態で保存する方法です。提供時には再加熱してから食器に盛り付けるだけのため、人手不足に悩む現場でも少ないスタッフで対応が可能です。
食材本来の味を引き出す
ナリコマのクックチルでは、食材の旨味や栄養を急速冷却によって封じ込めます。再加熱しても品質はそのままなので、できたてのおいしさのまま提供が可能です。おいしい病院食のために暖かいものは暖かく、冷たいものは冷たく提供します。また、あらゆる調理機材を組み合わせ、素材のおいしさを最も活かせる方法を追及しながら製造しています。このような工夫により味だけでなく食感や香りなどもしっかり味わえ、患者さまにとってより満足度の高い食事となるでしょう。
見た目からも「おいしい」を感じられる
おいしさを感じるのは、なにも味覚だけではありません。嗅覚や視覚から得た情報もとても大切で、特に視覚からの情報が8割を占めるのだそうです。ナリコマのクックチルでは、食材の色や食感を保ちながら、盛り付けや彩りに工夫を凝らしています。食欲を刺激する見た目で、毎日の食事の時間が楽しみになるでしょう。
ナリコマなら現場のサポートも行っていますので、美しい盛り付け方を学べる説明会を開催し、調理業務が不慣れなスタッフでも、安心して業務にあたることができます。

食形態の変更にも柔軟に対応できる
固形物を食べにくい患者さまにはミキサー状やゼリー状に加工した食事を提供し、安全に食事を楽しんでもらえるよう工夫する必要がありますよね。食形態変更にも素早く対応できるため、患者一人ひとりに最適な食事の提供は大切なポイントです。
ただ、嚥下力・咀嚼力に合わせた食形態を提供する場合、刻んだりすりつぶしたり、食材の加工には手間がかかってしまいます。ナリコマのクックチルなら、すでに調理済みの状態で届くため、あとは温めて提供するだけです。スタッフの負担削減にも役立ちます。
2024年からは、ミキサー食とゼリー食は高性能な機器を使用した新製法で製造されるようになりました。少ない量でもしっかり栄養を取れるように改良され、低栄養に陥ってしまいがちな高齢者のケアにも役立ちます。
おいしい病院食ならナリコマにご相談ください!

病院食は、患者の治療を支える土台となるものです。栄養補給に重きを置いていたかつての病院食から、現在では見た目も味もおいしい病院食へと各段に進化しています。
ナリコマのクックチルは、病院の給食部門が抱えるさまざまな課題解決と同時に、高品質でおいしい病院食を提供いたします。病院での食事提供に関するお悩みがあれば、ぜひナリコマへお気軽にご相談ください。抱えている問題を洗い出し、解決に向けてのお手伝いも致します。
ナリコマは、ご提供するおいしい病院食が、多くの患者とその家族に笑顔をもたらす未来を目指しています。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

医療・介護施設のBCP策定ガイド!安心安全な施設運営のために
地震や台風などの自然災害は、いつどこで発生するかわかりません。特に、医療や介護を支える病院や施設においては、災害が発生してもその役割を止めることなく継続する必要があります。
停電や断水、物流の停止などによって、通常の施設運営が困難になるケースも少なくありません。こうした緊急時に備えるために欠かせないのがBCP(事業継続計画)です。BCPとは、災害や緊急事態が発生した場合でも、業務を継続・早期復旧させるための計画で、特に命を預かる医療・介護施設にとってBCPの策定はとても重要になってきます。
今回は、災害時における医療・介護施設が直面する課題や対策方法などについて詳しく解説していきます。いざという時に備え、今からできる準備を一緒に考えていきましょう。
-

病院給食が約25年ぶりに値上げ!費用算出方法や物価高騰への対策を解説
病院給食は、その名の通り、主に入院患者さんに提供されています。価格は長らく据え置かれてきましたが、2024年6月1日に値上げが行われたことで注目を集めました。今回の記事は、この「病院給食の値上げ」をテーマにお届けします。
病院における給食の重要性や、値上げに至った背景などを詳しく解説。近年さまざまなところで影響を及ぼしている物価高騰への対策についてもまとめてみました。ぜひ最後までお読みください。
-

給食業界における最大の課題!コスト高騰化を乗り切る解決策とは
近年は数多くの商品やサービスの値上げラッシュが続いており、多種多様な業界はもちろん、消費者にも大きな影響を及ぼしています。食品や日用品の買い出しで「高くなった」と実感している方は少なくないでしょう。値上げの主な理由は、生産費や人件費といった各種コストの高騰化。この件は、給食業界においても最大の課題として解決が求められています。
本記事では、今や身近なテーマともいえるコスト高騰化について解説。詳しい要因を見ながら、給食を必要としている施設の現状や具体的な解決策などをお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。
コストに関する記事一覧
-

今後どうなる?給食業界の課題と将来性を詳しく解説
給食は、保育所や学校、病院、老人ホームといったさまざまな施設で提供されています。施設を利用する人々にとって、給食は健やかな生活を送るために欠かせないものでしょう。ところが、その一方で、現在の給食業界は大きな課題をいくつも抱えています。
今回の記事で取り上げるテーマは、給食業界の将来性。近年における業界の動向や解決すべき課題を挙げ、今後の展望について解説します。ぜひ、最後までお読みになってください。
-

給食委託会社との良好な付き合い方
給食業務における人手不足やコストなどの悩みを抱えているときに、給食委託会社の利用で解決できることがあります。しかし、場合によっては新たな問題が生じることもあるのが難点です。メリットやデメリットもあり、委託というスタイルによって今までできていたことが簡単にできなくなることもあるでしょう。
給食委託会社の利用によるデメリットでは、関係の構築に時間がかかることがしばしば挙げられます。これは単にやり取りに時間がかかるだけでなく、いくつかのトラブルが生じて、解決するまでの時間も含まれるでしょう。給食委託会社と依頼する側のトラブルは、残念ながらさまざまにあり、給食委託会社と良好な関係を構築することは難しく複雑であることもわかります。
今回は、給食委託会社を利用する際の関係構築の重要性と共に、どうすれば良好な付き合い方ができるのかを解説します。トラブルを防ぐためのポイントを押さえた関わり方や、トラブルが起きた際の早急な解決ができるように、給食委託会社の利用の際には改めて意識しておきましょう。 -

高齢者の食事を支える配食・宅食!サービスの違いや福祉施設での活用について
高齢者の食生活にはさまざまな課題があります。この食にまつわる課題解決に役立つのが、配食・宅食サービスです。この記事では、高齢者の抱える食事課題に触れながら、配食・宅食サービスの活用で得られるメリット、配食と宅食のサービスの違い、配食サービスが福祉施設にもたらす利益について解説します。