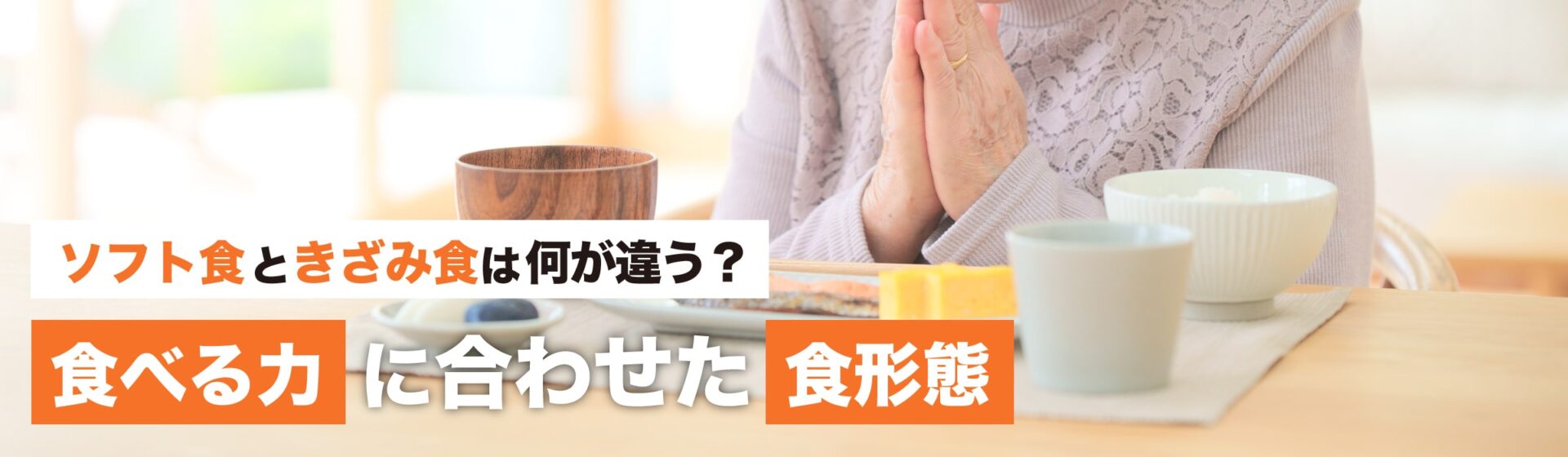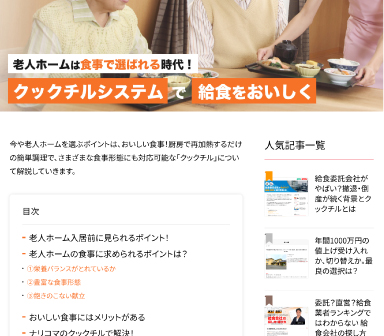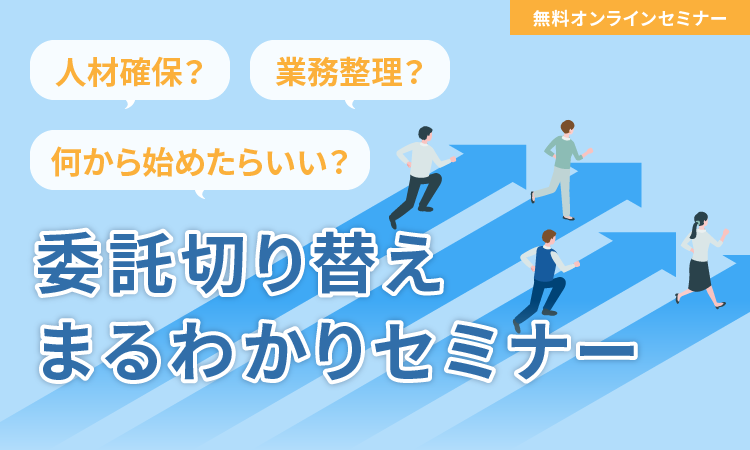どんな人でも、高齢になると咀嚼したり飲み込んだりする力が衰え、そこに個人差も生まれます。そういった個別の事情にも対応しやすいのが、介護食の利点です。
今回の記事は、介護施設や医療施設で多く導入されている介護食のうち、ソフト食ときざみ食の違いに注目します。ミキサー食や流動食など、そのほかの介護食についても種類別に解説。記事の後半では、介護食の新しい基準として浸透してきたスマイルケア食とユニバーサルデザインフードを取り上げます。
目次
ソフト食ときざみ食の違い
まず、ソフト食ときざみ食について詳しくご説明しましょう。
ソフト食は、軟菜食や軟食、やわらか食とも呼ばれています。かむ必要がほとんどなく、誤嚥しにくいため、咀嚼する力と飲み込む力が弱ってきた方に向いている食事です。歯茎や舌で潰して食べられるように、食材を丁寧に調理し、やわらかな食感に仕上げます。手間と時間はかかりますが、味や見た目が普通食に近いことは大きなメリット。料理がおいしそうに見えないことによる食欲減退を防ぎます。
一方、きざみ食は食材を5mm〜2cmほどに細かく刻んだ食事です。かむ動作は少なくなりますが、口内で食材がバラバラになりやすいので、ソフト食よりも誤嚥の可能性が高め。咀嚼する力が弱っていても、しっかり飲み込める方に向いています。食材を刻む手間はありますが、普通食に近い味や見た目です。ソフト食と同様、食欲減退の防止にもつながります。
以上のことからまとめると、ソフト食ときざみ食の違いは、食材の状態と飲み込みやすさの2点です。反対に、共通して重視されているのは食べやすさの部分。これは記事後半で取り上げるスマイルケア食やユニバーサルデザインフードにも関係しているので、念頭に置いておきましょう。
続いては、ミキサー食や流動食なども含む介護食全体について種類別に解説します。
介護食の種類を解説!

普通食だけでは対応が難しい状況を豊富なバリエーションでサポートするのが介護食。本項目では、そんな介護食を種類別に解説します。
介護食の種類①ソフト食
ソフト食は、食材をやわらかく調理した食事のこと。介護食の中では最も普通食に近いとされています。
介護食の種類②きざみ食
きざみ食は、食材を細かく刻んだ食事のこと。ソフト食と並び、普通食にかなり近いとされる介護食です。
介護食の種類③ミキサー食
ミキサー食は、食材をすり潰し、なめらかなポタージュ状にした食事のこと。食材をミキサーにかけ、だし汁やスープなどを加えて伸ばすのが一般的なレシピ。水分量が多いと口内でまとまりにくいので、のどに詰まらせたり咳き込んだりしないように、適度なとろみをつけます。ドロドロした見た目から、普通食との違いを強く感じる人が多いでしょう。
介護食の種類④ペースト食
ペースト食は、ミキサー食の一種。食材をミキサーですり潰し、粘り気が程よく残るように調整します。ミキサー食と比べて水分量が少なく、誤嚥しにくいのが特長です。ミキサー食と同様、見た目は普通食と大きく異なります。
介護食の種類⑤ムース食
ムース食はソフト食の一種で、すり潰した食材にとろみをつけて固め直した食事のこと。食感がやわらかく、舌などで潰して食べられます。彩りや形にこだわって調理することも可能。ミキサー食やペースト食と比較すると、普通食の見た目にやや近くなります。
介護食の種類⑥ゼリー食
ゼリー食は、すり潰した食材をゼラチンや寒天で固め直した食事のこと。その名の通り、飲み込みやすいゼリーのような食感です。ムース食と同様、普通食の見た目に近くなるよう成形することができます。
介護食の種類⑦流動食
流動食は、水のように飲める食事のこと。重湯(お粥の上澄み)や具なしの汁物などが流動食に分類されます。限りなく液状になっており、ほかの介護食と比べると栄養価はあまり期待できません。
続いては、既存の介護食に新たな基準をもたらしたスマイルケア食とユニバーサルデザインフードについて解説します。
スマイルケア食とユニバーサルデザインフードとは

「ソフト食ときざみ食の違い」の項目で、介護食の食べやすさがスマイルケア食とユニバーサルデザインフードにも関係しているとお伝えしました。そのことを踏まえつつ、それぞれについて解説します。
スマイルケア食とは
スマイルケア食は、市販されている介護食品の新しい呼び名です。平成25年2月から農林水産省主導で検討が進められ、のちに呼び名が決定しました。咀嚼する力や飲み込む力の程度に合わせて食品が選べるよう、スマイルケア食識別マークを以下のように設定し、表示しています。
「青」マーク
かむ力と飲み込む力に問題はないものの、健康維持のために栄養補給が必要な人向けの食品です。
「黄」マーク
かむことが難しい人向けの食品です。「黄2(かまなくてよい食品)」「黄3(舌で潰せる食品)」「黄4(歯茎で潰せる食品)」「黄5(容易にかめる食品)」の4段階に分かれます。
「赤」マーク
飲み込むことが難しい人向けの食品です。「赤0(ゼリー状の食品)」「赤1(ムース状の食品)」「赤2(ペースト状の食品)」の3段階に分かれます。
スマイルケア食の考え方では、栄養価や食べやすさだけでなく、味のおいしさや見た目の良さ、入手しやすさなどへの配慮も重要です。治療食や病院食、カプセルや錠剤などの特殊な食品は対象外となっています。
ユニバーサルデザインフードとは
ユニバーサルデザインフードは、日本介護食品協議会が考案した規格です。ソフト食やミキサー食などの介護食を咀嚼する力と飲み込む力の程度に合わせて区分し、ロゴマークと一緒に表示。「区分1(容易にかめる)」「区分2(歯茎で潰せる)」「区分3(舌で潰せる)」「区分4(かまなくてよい)」の4つに分けられています。
また、食べ物や飲み物に混ぜて使えるとろみ調整食品にもユニバーサルデザインフードのマークを表示。とろみの強さが4段階で表示されており、食べる人に合わせた食品選びをサポートします。
ナリコマの介護食の特長
今回はソフト食ときざみ食の違いに続き、介護食の種類、スマイルケア食とユニバーサルデザインフードの解説をお届けしました。では最後に、ナリコマグループの介護食を簡単にご紹介しましょう。
ナリコマのベーシックな献立サービス「すこやか」は、和食から洋食まで幅広く、365日異なる献立が魅力です。季節に合わせた食材や郷土料理なども取り入れ、食本来の楽しみを損なわず、毎日飽きのこないおいしさを追求しています。もちろんアレルギーの個別対応も可能です。
普通食に加え、介護食は3種類ご用意。食材の食感まで楽しめるソフト食、味や香りにこだわったミキサー食、つるんと食べやすいゼリー食からお選びいただけます。量が少なく低栄養になりがちなミキサー食とゼリー食には、エネルギー源となるMCTオイルを使用。よく取り上げられる介護食の問題点も、しっかりカバーしています。
クックチルやニュークックチルに対応しているため、コストを削減しながら現場のオペレーションもスムーズに。導入前後も充実したサポート体制で、運営面も丁寧にお手伝いします。
高齢者施設、病院の介護食はナリコマにおまかせ
ソフト食ときざみ食の違いをはじめ、バリエーション豊かな介護食についてよくご理解いただけたかと思います。高齢社会への対応が欠かせなくなる今後は、スマイルケア食やユニバーサルデザインフードもさらに広く浸透していくのではないでしょうか。介護食の導入をご検討の際には、ぜひ本記事の内容もご参考になさってください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

医療・介護施設のBCP策定ガイド!安心安全な施設運営のために
地震や台風などの自然災害は、いつどこで発生するかわかりません。特に、医療や介護を支える病院や施設においては、災害が発生してもその役割を止めることなく継続する必要があります。
停電や断水、物流の停止などによって、通常の施設運営が困難になるケースも少なくありません。こうした緊急時に備えるために欠かせないのがBCP(事業継続計画)です。BCPとは、災害や緊急事態が発生した場合でも、業務を継続・早期復旧させるための計画で、特に命を預かる医療・介護施設にとってBCPの策定はとても重要になってきます。
今回は、災害時における医療・介護施設が直面する課題や対策方法などについて詳しく解説していきます。いざという時に備え、今からできる準備を一緒に考えていきましょう。
-

病院給食が約25年ぶりに値上げ!費用算出方法や物価高騰への対策を解説
病院給食は、その名の通り、主に入院患者さんに提供されています。価格は長らく据え置かれてきましたが、2024年6月1日に値上げが行われたことで注目を集めました。今回の記事は、この「病院給食の値上げ」をテーマにお届けします。
病院における給食の重要性や、値上げに至った背景などを詳しく解説。近年さまざまなところで影響を及ぼしている物価高騰への対策についてもまとめてみました。ぜひ最後までお読みください。
-

給食業界における最大の課題!コスト高騰化を乗り切る解決策とは
近年は数多くの商品やサービスの値上げラッシュが続いており、多種多様な業界はもちろん、消費者にも大きな影響を及ぼしています。食品や日用品の買い出しで「高くなった」と実感している方は少なくないでしょう。値上げの主な理由は、生産費や人件費といった各種コストの高騰化。この件は、給食業界においても最大の課題として解決が求められています。
本記事では、今や身近なテーマともいえるコスト高騰化について解説。詳しい要因を見ながら、給食を必要としている施設の現状や具体的な解決策などをお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。